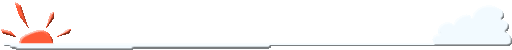
井上成美 山本五十六 米内光政 山本権兵衛 秋山真之 山口多聞 加藤友三郎 角田覚治
大西瀧治郎 小澤治三郎 堀 悌吉 岡田啓介 伊藤整一
海軍兵学校人物伝 7海軍生みの親 勝海舟文政6年(1823年)旗本・小吉の子として江戸本所に生まれる。名は麟太郎・安房・のち安芳。父・小吉は江戸屈指の剣客として鳴らしたが、大変な暴れん坊で、乱暴が過ぎ、座敷牢に入れられ、37歳の若さで隠居の身になる。そんな小吉が42歳の時に書いた『夢酔独言』の中には、野良犬に噛まれ、瀕死の重傷を負った幼少の海舟を「あの剣術つかいは、子を犬に食われて気が動転したそうな」と噂されるほど、70日間にわたり、必死になって看病したことが記されている。その時の、父・小吉の看病がなければ、その後の海舟もなかったと言えよう。海舟は、剣術を中津藩士島田虎之助に学び、島田の忠告により、西洋兵法と蘭書を学び、筑前藩士永井青崖の指導を受ける。嘉永6年、ペりーの率いる米国軍艦4隻が浦賀に入り、天下騒然となった際、海防意見書を要路に提出し、ここに海舟と日本海軍の関係が始まる。海軍の必要性を説いた、『海国兵談』を著した林子平が、幕府により牢獄に投ぜられてから60年後のことである。 嘉永7年、ペりーが再び浦賀に来航した年、オランダ国王・ヴィルレム三世は、使節を我国に派遣し、欧州の戦争を知らせ注意を喚起し、我国から帆船、蒸気船の建造依頼を引き受けるが、引き渡し時期が提示できないため、蒸気船スームビング(観光丸)を贈り、艦長一同を差し向け、必要な諸学を伝授する。幕府は、ついに長崎海軍伝習所を開設し、諸藩から伝習生百数十人を集め、海舟を生徒監に命ずる。歴史を動かす人物・勝海舟が、最下級武士から歴史の表舞台に躍り出てきた。こうして、日本海軍は長崎から始まった。 幕府は、安政4年築地講武所に軍艦教授所を設置、長崎伝習所卒業生の一部を呼び寄せ、百余人の卒業生は観光丸を操舵し横浜に入港する。築地軍艦教授所は海軍操練所と改称、さらに明治に入り、海軍兵学寮となる。これが後の、海軍兵学校の前身である。勝海舟は、学成り軍艦操練所教授方頭取を命ぜられ、長崎伝習所は中止となる。 安政5年、ハリス二度目の来朝。日米修交通商条約を調印し、幕府は、米国ワシントンに使節を派遣することになり、同7年、外国奉行・新見正興、村垣範正を送ることにする。ところが、遠洋航海に未だ習熟せず、また、船の規模が小さく、多人数が乗船できぬとの理由から、米艦ポーハタンに便乗する。しかし、一国の使節が外国の軍艦に護送されるとは、国辱ものであるとの声に押され、幕府は別個に軍艦咸臨丸(250㌧・オランダ建造)で、軍艦奉行・木村摂津守を派遣し面目を保とうとした。艦長(船将)は、勝麟太郎。 木村摂津守喜毅は、号を芥舟(かいしゅう)。もう一人の「海軍生みの親」と言える。木村は「海軍建設こそが日本国防の道」との使命感から、私財を全て投げうって、咸臨丸に乗り込んだ。十数年後、木村が次のように語っている。「幕府は大した費用を出さない。といって水夫らに手当てを与えて労を謝さぬわけにもゆかないだろう。金がないからと私が辞職してしまえば、ほかに代わる人がいない。そうなれば水の泡だ。日本海軍の端緒をひらこうという破天荒の大盛挙も、すべて瓦解してしまうことになろう。」 文久2年、海舟は軍艦奉行並を命ぜられ、将軍家茂から海軍の議で海軍整備について質問される。これに対し、海舟は「軍艦は数年を出ずして整うとも、人員は習熟できませぬ。イギリスの盛大も300年を経て今日に至ったもの。問題は人間や船の数にあらず。人民が学術はもちろん、勇武他を圧伏するに足らなければ、真の防御は立ち難い。学術進歩して、その人物が出ることこそ肝要であります」と答えている。 文久3年、海舟は兵庫小野浜に兵庫海軍操練所を設立。門下生に、坂本龍馬、伊東四郎(後の伊東祐亨)伊達陽之助(後の陸奥宗光)等その後の歴史に名を連ねる、蒼々たる人物を擁し、海舟の私塾の観があった。このため、幕府が警戒し、圧力により閉鎖。因みに、龍馬は以前、海舟を斬ろうと、北辰一刀流・千葉周作の甥・重太郎と屋敷に乗り込むが、その人物に惚れ込み師事することになる。土佐藩の岡っ引き・岩崎彌太郎が、龍馬の命をつけ狙ううちに、海援隊の金庫番となり、後の、三菱の基礎を創ったのも、奇しくも歴史の因縁と言える。江戸城無血開城となる、勝海舟と西郷吉之助の談判設定に奔走したのも龍馬である。龍馬は、「薩長連合」や明治憲法の基礎とも言うべき「船中八策」、海援隊を組織するなど、海舟同様、当時の時代背景からすると、国際的な視野は驚異的とも言える。まさに、「英雄が時代をつくるのではなく、時代が英雄を生む」と言える。 明治に入っても海舟は、外務大丞、兵部大丞、海軍大輔、参議兼海軍卿、枢密顧問官などを歴任し、明治32年77歳でこの世を去る。 参考文献 新名丈夫(評論家)諸論文 『竜馬がゆく』他 |
次ページへ(加藤友三郎)
「勝海舟」関連書籍