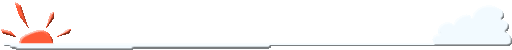
井上成美 山本五十六 米内光政 山本権兵衛 秋山真之 山口多聞 勝海舟 角田覚治
大西瀧治郎 小澤治三郎 堀 悌吉 岡田啓介 伊藤整一
海軍兵学校人物伝 8軍縮の立役者 加藤友三郎文久元年(1861年)広島市大手町に生まれる。海軍兵学校7期卒。同期には元帥・島村速雄、藤井較一、吉松茂太郎と4名の大将がいる。海軍大臣、総理大臣を歴任。とくに、海相は7年10ヶ月の長きにわたり務める、子爵、元帥。ワシントン会議の際、欧米の記者が、その風采の上がらぬ容姿、風貌から「ろうそく」の渾名を付け軽視するが、加藤の人物に触れるや「危機の世界を絶えず明るく照らす偉大なろうそく」との評価に変わる。海相時代に艦政本部の改組、航空隊の創設、学校制度の改革、研究部の設置など実施。明治24年大尉の時、造兵監督官として英国に出張し、同国で建造・竣工した軍艦「吉野」の砲術長として、砲術の実習を兼ね、日本への回航に乗り込む。27年3月帰国するや否や、3ヶ月後には日清戦争に出動する。7月25日朝、豊島沖海戦により開戦の火蓋が切られたが、砲術長加藤の存在を遺憾なく発揮することになる。「吉野」は、「秋津州」「浪速」の2艦を率いて朝鮮沿岸を警戒中、清国軍艦「済遠」「広乙」と遭遇する。また、敵艦「操江」と英国旗を掲げ、多数の清国陸兵を輸送中の汽船「高陛号」を発見し砲撃、「広乙」は座礁自爆、「操江」は捕獲、「高陛号」を撃沈した。8月には、威海衛攻撃に参加。9月16日には、黄海の海戦に大いに活躍した。日本海軍の損害は大きかったが、沈没艦はなく、逆に清国の喪失5艦。「吉野」から放たれた初弾が命中し、敵艦「超勇」「揚威」を撃沈した。これも、加藤砲術長の腕前による。 日露戦争時加藤は、司令長官上村彦之丞の第2艦隊参謀長として、旗艦「出雲」に乗船する。ここで加藤らは、手痛い目にあうことになる。明治37年3月、第2艦隊はウラジオ艦隊撃破の命令を受けるが、これを補足できず、その結果、運搬船「金州丸」「常陸丸」「佐渡丸」が次々と撃沈され、多数の陸兵を失うことになる。その後、ウラジオ艦隊は、津軽海峡を通過し、伊豆南岸にまで現れ商船数隻を撃沈する。 国民の怒りは頂点に達し、「上村艦隊は何をやっているのか」と、上村、加藤らの留守宅は投石を受ける始末であった。議会でも代議士が「濃霧濃霧といいわけをするが、さかさに読めば無能なり。上村艦隊は無能の一語につきる」と演説し、揶揄した。しかし、8月14日上村艦隊は、蔚山沖でウラジオ艦隊3隻と遭遇し、旗艦「リューリック」を撃沈し、他の2隻は遁走する。「リューリック」は、沈没する最後の最後まで後部の砲門で撃ち続けるのを止めようとはしなかった。「出雲」艦橋でこれを見ていた上村は「敵ながらあっぱれだ」と全隊集合を命じ、溺れるロシア将兵627名を救助し、武士道精神を世界に知らしめた。 明治38年1月、加藤は第1艦隊兼連合艦隊参謀長となり、5月27・28日の両日の日本海海戦に旗艦「三笠」艦上で作戦を指揮した。バルチック艦隊と同航しつつ、「わが半ばを失うとも敵を撃滅せずんばやまず」との捨て身の「丁字戦法」(敵前180度回頭)を展開する。東郷司令長官と加藤は弾丸あめあられの中、「三笠」の艦橋に立ちつくし、弾が飛んできても安全な司令塔には入ろうとしなかった。指揮官のこの姿は、当然兵士の志気を鼓舞したことは言うまでもない。 大正2年、第1艦隊司令長官となった加藤は、第1次大戦に青島攻略などに出動、その後海相を歴任後、大正11年に総理大臣となる。しかし、加藤の最大の功績は、大正10年12月ワシントン軍縮に全権で、英、米、仏、伊、ベルギー、オランダ、ポルトガル、中国の各国代表と共に参加、「八・八艦隊」計画以来の、日本の軍備増強による財政破綻を救ったことにある。 この計画は、戦艦、巡洋艦各8隻を基幹とする艦隊で、明治42年から着手し、大正16年に完成予定であったが、国力不相応であった。大正9年に襲った世界恐慌が大きく計画の前に立ちはだかり、「八・八艦隊」の予算だけで国家予算の29%を占めるに至った。このことを一番理解し、心を痛めていたのが、何あろう「八・八艦隊」の推進者であった加藤その人であった。しかも「八・八艦隊」は、加藤自身の「国防論」からも逸脱するものであった。 因みに、ワシントン会議の海軍協定は、以下のようなもである。 1,英、米、日の主力艦比率を五、五、三とする 2,建造中の主力艦を廃棄し、且つ10年間建造を中止する 3,戦艦限度は3万5千㌧、16インチ砲、航空母艦は2万7千㌧8インチ砲とする 4,巡洋艦限度を1万1万㌧、8インチ砲とし、建造量を制限せず 5,太平洋前進根拠地の現状を約す 6,本協定の有効期間を10ヶ年とする 我国は、主力艦の保有比率7割を要求したが、通らなかった。対米比率7割を強硬に主張する随行員に対し、加藤は「7割なら安全で6割なら危険であるという根拠を、もっと研究しようではないか。主張する以上は、根拠があるはずだ。たとえば、6割5分ならこうだ、というようなしっかりした数字的根拠があるはずではないか。観念論では駄目だ。兵術論を言い張っても駄目である」と言って窘めた。海外では、日本の勝利との論評であった。 ワシントン軍縮会議後の、大正11・12年(53・54期)の生徒募集は、52期の300名から各50名に減り、難関中の難関・海軍兵学校の門は、ますます狭き門となった。 米国提案の五・五・三の比率受諾を決意した加藤は、海軍省宛伝言を口述し、堀悌吉中佐に次のように筆記させた。「国防は軍人の専有物にあらず。戦争もまた軍人にてなし得べきものにあらず。国家総動員してこれにあたらざれば目的を達しがたし。・・・平たくいえば、金がなければ戦争ができぬということなり。・・・日本と戦争の起こるprobability(可能性)のあるのは米国のみなり。仮に軍備は米国に拮抗するの力ありと仮定するも、日露戦争のときのごとき少額の金では戦争はできず。しからばその金はどこよりこれを得べしやというに、米国以外に日本の外債に応じ得る国は見当たらず。しかしてその米国が敵であるとすれば、この途は塞がるるが故に・・・結論として日米戦争は不可能ということになる。国防は国力に相応ずる武力を備うると同時に、国力を涵養し、一方外交手段により戦争を避くることが、目下の時勢において国防の本義なりと信ず。すなわち国防は軍人の専有物にあらずとの結論に達す」(旧海軍記録文書) この加藤友三郎の口述伝書は、敗戦の日まで、海軍省の金庫に機密文書として封印され、日の目を見ることはなかった。 参考文献 新名丈夫氏(評論家)諸論文 『日本海軍の興亡』他 |
次ページへ(角田覚治)
「加藤友三郎」関連書籍