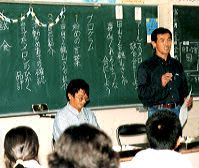
とうとうアールスメロン試食会にこぎつけた
(右がヒロアキさん、左がツルヤマさん)
前号で紹介した「スイカって、こうやって育つんだよ」のホームページが完成した際、小佐井さんのお母さんは「これを見れば、誰にだっておいしいスイカが作れそうですね。」と言われた。私は即座に「無理ですよ。だって、農家の方にはごく当たり前でも、私たちには想像もつかないようなノウハウが、たくさんあるんですから。」と応じたものだ。それを、こんな形で自ら実感することになろうとは…。
○「メロン栽培は絶対に無理」と言われたが…
平成八年七月にオープンした川上小のホームページ。「目玉になるような、おもしろいアイディアはないかな?」「オープンと同時に生まれた動物の、成長の様子を追っていったら?」「それはおもしろい。でも動物だったら、なかなか成長していかないよ。」「だったら、植物がいいんじゃない。」「そう言えば、秋には(前々号で登場した)ヒロアキさんがアールスメロンを収穫するので、今はちょうど種子まきの時期では?」「そうだ、学級で育てたメロンの様子をホームページ上に公開し、そこでヒロアキさんの育てたものと比較したり、アドバイスを受けたりしていくといいぞ。」「うん、これはすばらしい!」
さっそく、ヒロアキさんに連絡をとる。しかし…「学校で育てるなんて、とんでもない。無理です。絶対に育ちっこないですよ。何個植えても一緒です。」だが、私も引き下がれない。先の小佐井さんの言葉を例に引きながら、「うまく育たないのも、それはまたそれで、貴重な勉強ですから。」と言ってヒロアキさんを説得。どうにか協力を取り付ける。
○ネットの入ったメロンを四個も収穫
七月十五日、ヒロアキさんより届いたアールスメロンの種子十粒を植える。種子には、「せっかく育てるからには、うまく育ってほしい」という願いから、育て方を詳細に記した図解入りの虎の巻が添えてあった。その中で特に強調されていたのは、「絶対に雨に当てないように」ということ。そこで、移動しやすいように鉢植えして、ベランダのひさしの下で育てることにした。おかげで終業式直前の台風八号、盆前の十二号も、室内に取り込んでうまく被害を免れた。そのかわり、何分酷暑中の夏季休業日のこと。ちょっと天気がいいと、鉢はすぐカラカラに乾いてしまうので、朝夕二回の水かけに、ほぼ毎日欠かさず通ったものだ。その甲斐あって、八月末には無事交配を終えることができた。ヒロアキさんから「メロンの場合、交配して実が成る段階までいけたら大したものです」と言われていた、まさにその段階までこぎつけたのだ。嬉しかった。
もっとも、そこからがまた長い道のりだった。成長点を止めると、途端に病気が出始める。それだけ株自体の体力が付いていなかったためだ。おまけに、次々に青虫がはびこり、ついには実までかじられてしまう。しかし、ベランダは子どもたちが裸足で行き来するので、農薬が使えない。その分人海戦術で対抗するのだが、とても追いつかない。本当に、自然は厳しいと痛感した。さらに一つの鉢が転倒し、大切な実が割れてしまったりもした。
それでも十月中旬には、一応ネットの入ったメロンを四個も収穫できた。嬉しかった。
○感激のアールスメロン試食会
「五年一組が収穫したメロンを、ヒロアキさんに実際に見てもらって、どんな出来具合か評価してほしい。」「ヒロアキさんのメロンとどう味が違うか、食べ比べてみたい。」そんな声が、子どもたちから湧き起こった。ありがたいことに、ヒロアキさんに加えて(前々号に登場した)ツルヤマさんも協力して下さることになり、十月二十五日にお二人を招いて、「アールスメロン試食会」を行うことになった。
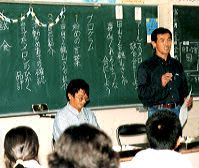
とうとうアールスメロン試食会にこぎつけた
(右がヒロアキさん、左がツルヤマさん)
一.はじめの言葉→ヒロアキさん・ツルヤマさんの紹介
子どもたちは、これまでネットワーク上でしか知らなかったヒロアキさんとツルヤマさんに、ようやく会える嬉しさで目を輝かせていた。
二.育てたメロンとの比較
ヒロアキさんが持って来て下さったメロンと自分たちが育てたメロンとを、外見から比較し、「評価表」にすべて五点満点で記入させた。同時に、ヒロアキさん・ツルヤマさんにも評価をしていただいた。その結果は、以下の表の通りとなった。子どもたちは、あらためて商品価値のあるメロンを作ることの難しさを実感したようだった。
| アールス・メロン 「外見」の評価 | |||||
| メロン の名前 |
自己評価 (平均) |
ヒロアキさんの評価 | 鶴山さんの評価 | ||
| 点 | ひとこと | 点 | ひとこと | ||
| みやびA | 2.4 | 1 | 虫が食べている | 2 | 虫に喰われたのが残念 |
| セイヌA | 3.0 | 2 | アンテナが片方ない | 3 | ネットに傷がついている |
| セイヌB | 3.1 | 2 | ネットがあらい | 4 | 水管理でネットの入りが不規則 |
| セイヌC | 1.4 | 1 | ネットがない | 1 | ネットが入っていません |
| ひろあき | 5.0 | 4 | 小さい | 5 | さすが!! |
三.試食
それぞれのメロンを実際に食べ、五点満点で評価するとともに、味や舌触り・その時の気持ちなどを簡単にメモさせた。また、ヒロアキさんに糖度計を使って糖度を計っていただいた(計測値は、子どもたちには教えなかった)。結果は表2の通りとなった。子どもたちは、自分たちの作ったメロンが意外においしかったのを喜ぶ一方、ヒロアキさんのメロンのあまりのおいしさに、びっくりしていた。
| アールス・メロン「中身(味)」の評価 | ||||||
| メロン の名前 |
自己評価 (平均) |
ヒロアキさんの評価 | 鶴山さんの評価 | 糖度 | ||
| 点 | ひとこと | 点 | ひとこと | |||
| みやびA | 3.1 | 4 | よくできました | 3 | ふつう | 12.2 |
| セイヌA | 3.6 | 5 | すごい | 5 | 甘みがありおいしい | 14.8 |
| セイヌB | 2.6 | 4 | もう少し | 3 | ふつう | 10.4 |
| セイヌC | 1.3 | 3 | 水分がない | 2 | 水分が少ない | 11.0 |
| ひろあき | 4.9 | 4 | 熟しすぎ | 5 | 追熟しすぎ | 15.4 |
四.感想発表
メモをもとに班で話し合わせ、代表に発表させた。以下にその一例(一部)を掲げる。
|
みやびAは、少し味がないのがざんねんでした。セイヌAは、見た目よりすごく甘くておいしかったです。まるでハチミツをなめたような味でした。セイヌBは、ものすごくへんな味がしました。セイヌCは、見かけよりすごくまずくて、かたいし、水けがありませんでした。ヒロアキさんのメロンは、やわらかすぎたけれど、とろりとしてておいしかったです。 |
子どもたちの感想は、糖度計の値とぴったり一致していた。子どもたちの舌の確かさに、我々大人たちは大いに驚かされたものだ。
五.ヒロアキさん・ツルヤマさんのお話を聞く
ヒロアキさん・ツルヤマさんに、メロン・トマト作りに関する苦労や日ごろの思い、今日の試食会の感想などを語っていただいた。ヒロアキさん・ツルヤマさんも、有意義な交流会ができたことをたいへん喜んでおられた。
六.先生の話→終わりの言葉
アッと言う間に過ぎた一時間。名残を惜しみながら、試食会の幕を閉じた。
○農家の前で「メロンづくり」を発表した子どもたち
実は、これには後日談がある。H九年三月、熊本県農業会議主催「ひのくにねっと会員の集い」で体験発表してほしいとの依頼が、私にあった。そこで学級から有志を募り、これまで紹介したスイカやメロン・トマトに関する実践を、六名の子どもたちがプレゼンテーションを交えながら発表した。これはたいへんな好評を博し、次にマイクを受け取った事務局長の平江さん(当時)など、「素晴らしいですねえ」と言ったきり、しばし言葉に詰まったくらいである。
さて、その後の「交流会」にもちゃっかり仲間に入れていただいた子どもたちだが、ここでさらに大人たちを感心させることになる。
|
<ある会員の「ひのくにねっと」電子掲示板への書き込み> さすがTAKANAO先生の生徒さんたちだなぁ、と感心したのは、交流会を締めた後、テーブル上に残った料理を見て、口々に「もったいな〜い」と言っていたことです。 |
お開きになった会場の、子どもたちが座っていた席の前には、すべてのテーブルからかき集められた、他ならぬアールスメロンの皮が、堆く積み上げられていたのである!!
|
「ネットワークの向こうには人がいる」 情報ネットワークは、人と人とが付き合っていく上での、距離や時間など物理的な制約を取り払ってくれる、極めて有効な手段です。しかし一方で、あまりの便利さ故に、つい相手との間合いをつかみ損なってしまうこともあるようです。 |